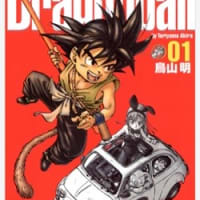「いつもってわけじゃないけど。締切前の修羅場のときはメシスタントが来てくれるし。編集から差し入れもある。自炊したことないな、食中毒が出たら困るし」
さりげなく末尾にホラーなこと言うな。
まさか、シチューに絵の具溶かしたり、コーヒーカップをインク壺にしてたり、ペンや筆でメシ食ったりしてないだろうな。そう考えたら、タコの切り身みたいなわかりやすいほうがいいのか、まさか消しゴムとまちがえたりはしないだろうけど。
「へ~え。売れっ子漫画家センセイはいいご身分ね? さぞや、いいもの食べてらっしゃるんじゃないのぉ」
「キュウリにハチミツかけると、メロンの味がしてうまい」
「それ、キウイのまちがいじゃない?」
「フルーツポンチにキュウリやニンジン入れてもイケる。彩りが美しい」
「それもう、ただのサラダじゃん」
プリンに醤油かけたらウニとか、みかんだとイクラになるとか。イチゴとマヨネーズで大トロになるとか。パレットで絵の具を混ぜるみたいに、いろんな食べ合わせのネタをぽんぽん振ってくる。キウイの話をしたあたりから、珍しく、会話に食いついてくるようになった。しかし、あたしはこんな与太話をしにきたんじゃないんだがな。でも、こんなふざけた舌音痴なハナシ、楽屋裏だってできそうになかった。極ウマ調味の味が、素人の掛け合わせでできるなんて知れたら、食品スポンサーに生涯敬遠されてしまうだろう。
「水と砂糖と塩とそのほか調味料。それさえありゃ、3本100円のキュウリだってキウイに化ける。黒豆だって、キャビアに見える。なにを食べたかじゃない。同じものを再現できるんだったら、つくったのが誰かもすぐに忘れる。けっきょく、みんな甘いか、辛いか、苦いか、酸っぱいか。刺激になる味が欲しいだけ。感覚はすぐに自分を裏切る」
「そういう麻痺した感覚相手に商売してんのが、あたしらのビジネスなんだわ。しゃーないわ」
篭盛りのキュウリのうちの1本がキウイになり、丸まるとしたマスクメロンになったりする。
そんなもんだわ、あたしらの業界って。イチかバチか、そういうバケモノじみた魔法の業界なんだもの。一千万ぶんに一個のメロンの陰で、清潔にパッケージングされて贅沢に食べ残される高級食材になれなくて、皮ごと消費されるようなままでいるのが、ゴロゴロいる。
「でも、味に当たりはずれが極端にないのがキュウリのいいところ。だから、ハチミツでも醤油でも塩でもなんでもよく溶け合う。海苔に巻かれて寿司にもなる。けっして、それひとつでは食の王様になれなくてもね」
「そりゃ、キュウリじゃ食卓のアイドルにはなれっこないわ」
「でも、メロンひとつじゃ人間、生きていけない。メロンが好きな奴は分け合おうとしないから」
「小難しいこと言うのね。あ~もお、その話パスパス」
腕組みして横目で嫌みな視線をおくってカッコつけたあたしだったけど、内臓はそうじゃなかった。ぐ~ぎゅるるるぅと盛大なお腹のチャイムが響いた。コンビニのビニ傘は嫌なのだと、手でも声でも言うことはできるのに、どうして胃腸はひもじさを隠してくれないのだろうか。
レーコが破顔一笑、笑い転げている。
こんな彼女をみるのははじめてだ。といっても、あたしたちは今日出会ったばかりなのに、前から見知っているもののように感じた。ほんの、ささいな、大キライがたまたまぴったんこしただけの仲なのに。それでも、スキだの、カワイイだの、うわべだけきゃいきゃい騒ぐだけの女子トークよりも楽だった。
あたしはお腹をかかえて真っ赤になって、うずくまった。
ふははは。悪の魔王みたいな勝ち誇った笑いをする。レーコのぶしつけな笑いは収まらない。
「ちょっと、いい加減、笑うのよやめてよ! あたしだって、お腹ぐらい空くわよ。人間なんだから」
今日は、というか、ここ数日マトモに食べていなかった。食べたのはバナナぐらいかな。ダイエット中だったし。そうだ、あたしはいま人間なんだった。この瞬間だけ、アイドルやめてもいいとさえ思った。出会ったばかりの素っ頓狂な漫画家と、タコの切り身を分け合う、あけすけな関係になれるのならば。この東京砂漠であたしにそんな人がいただろうか。
「…ごめん。おかしかったから。おやつだったらあるけど、食べる?」
「おやつって、まさか…」
ポッキーでお約束の両かじりじゃないだろうなって怪しんでたら、レーコが冷蔵庫から出してきたのはとんがりコーンだった。
食べかけだったのか、開封済みの銀いろの袋を丸めて輪ゴムで止めてあった。ちょっとだけ拍子抜け。ほっとしたような、がっかりしたような…って、あたし、何考えてんだろ。
「って、なんで、冷蔵庫に入れとくの? アンタ、バカじゃない? 湿って不味くなるでしょ」
「どうせ、その冷蔵庫、電気いれてないし」
「てか、なんでケータイまで…」
「うるさいから、そこに保管しといた。編集に捨てるなって言われたから」
レーコはさらりと言ってのけた。
ますます、こいつの生活がわからない。絵を描くこと以外の生活にはまったく無頓着といった感じだった。料理をするということに関心がないのだろう。
冷蔵庫どころか、テレビの中まで空っぽで野菜の貯蔵庫にしていかねない。想像するとアタマが痛くなってきた。というか、この部屋にはテレビすら見当たらない。
こいつはふだんの食事は酒のつまみみたいなものしか、食べてないのか。漫画家の不摂生って噂に聞いてたけど、やっぱ酷いもんだわ。平均寿命まで生きられないっしょ。というか、もはやニンゲンをやめてしまったのかもしれない。
スナック菓子の袋を開いたレーコは、口をあたしのほうへ向けた。あたしは、ぷいと横を向いた。
「いらない」
「そう?」
レーコは、ひとつを空に放り投げて、口でキャッチする。けっこう、うまい。妙な特技があるもんだ。締切が近い漫画家は手を汚さずにものを食う芸当を身につけるらしい。
ぐ~きゅるる。またひとつ、お腹の恥ずかしい音が鳴った。
欲しい、なんて言うな。金輪際、もう鳴いてくれるな。もう絶対に誰にも組み伏せられたくないならば。ご飯を奢ってやるだけで、札束で頬を撫でるだけで、女がからだを開くと思われるのは、もうたくさんだった。あたしは痩せた犬じゃない。餌がなけりゃ歌えない鳥じゃない。奥歯が痛いほどかみ合っている。
「おいしいよ、これ?」
「いらない」
っつうか、しれっと小指にはめて食わせようとすんな。
腹の虫はさっきほど大きくはないけれど、断続的に鳴っていて、お腹と背中の皮がくっつきそうなほど、飢餓感が募っていた。
そっか、中途半端にタコなんか口にしたのがいけなかった。そのうえに、メロンだのなんだのの話まで加えて、胃腸の消化作用を活性化させやがったのだ。へたにカロリーが少ないものを口にするとどんどん食べたくなっちゃう。こんにゃくゼリーといっしょだ。ぬるっとした喉滑りがたまらなくて、濡れた口内がまだ何か求めていた。
見せつけるように食べるレーコに、空き腹のせいもあっていらいらが募っていた。
「ねぇ、ほんとにいらないの?」
「うっさいわね! いらないったら、いらないのよ!」
レーコがさしだした袋の口を視界からどけようとして、手で弾いた。
袋の中からポップコーンが弾けるみたいに、三角のスナックが飛び出して床に散らばった。あ、マズいって思ったけれど、拾わなかった。
落ちたコーンを拾い集めてレーコは棄てていた。一週間ばかり掃除を怠っていたと見えて、床に舞っていた綿ぼこりを吸い寄せてしまったからだろう。袋は軽くなったが、まだいくぶん残っているようだった。
【目次】神無月の巫女二次創作小説「ミス・レイン・レイン」